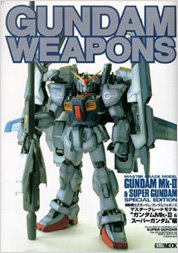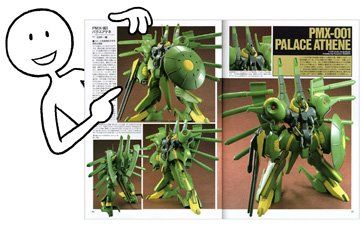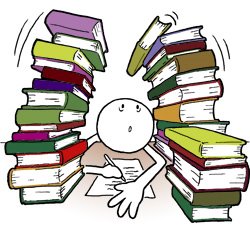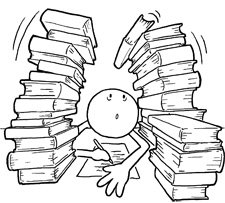アメリカと日本の間で在宅勤務
マンガ家になろうかとうつつを抜かしている大学時代、私は思った。ファックスマシン、FedExの輸送サービスや長距離電話の低コスト化のお陰で、たとえ日本に編集者がいてもなんとかアメリカからでもマンガを描けるかもしれない。
でも実際にマンガを描き始めたときには昔とは比べ物にならないほど世の中は便利になっていた。
大塚さんとマンガ本の企画を始めた時から電子メールで通信していた。たまに電話で話したこともあったが、電子メールの方が便利だった(安かったし)。特に都合が良かったのは、私の本業が終わり、うちに帰って夕飯を終わらせてマンガに専念する時間になると、ちょうど日本では労働時間が始まるということだった。
インターネットサービスの転送スピードは上がっていく一方なのでファイルを送る作業もそれに連れて良くなる一方だった。初めのうちはあらすじやシナリオを書いたテキストファイルだけを送っていた。描いたマンガの内容をチェックしてもらう時でもファイルを圧縮していたので、ページあたり1~3メガバイトで済んだ。最終的に印刷所へ送ったハーフトーンされたファイルは白黒であったため、もとの内容チェック用のファイルよりも小さかったので(高解像度な2400DPIであったにも関わらず)ファイルが重すぎたことはなかった(カバーイラストだけはかなりでかく、取り扱いが面倒だった)。
普通の郵便の方が便利だったのは編集作業の時だけだった。大塚さんは細かい編集をオンラインではやらず、プリンターで打ち出したページに赤ペンで編集を入れて国際郵便で送るのが一番簡単だった。
そのようにほぼ初めから最後までインターネットのファイル転送だけで間に合った。それでも何回かは日本に行って大塚さんと顔を合わせた。いつまでもインターネット上のバーチャルだけな存在でいるのも変だし、互いに知り合うためには直接会うのが一番である。
ある訪問中、大塚さんは私をマンガの編集者である清水さんに紹介してくれた。清水さんはあの「少年マガジン」の副編集長だったので、私はどうなるんだろうと少しビビった。でも全く心配することはなかった。彼はとても親切で、私に励ましのアドバイスなどを色々としていただいた。例えば「自分で描くのが面白くなかったり面倒な絵は、読者が読んでもそのように感じる」という知恵は今でも毎日マンガを描きながら意識している。

とても残念なことに、あれからそれほど経たないうちに清水さんは脳溢血で亡くなられてしまった。清水さんは大勢のマンガ家を育ててきた偉大な人である。私はいつも清水さんや父からなどのアドバイスを頭に入れているので、そういう人たちの影響が自分の作品の中で生き続けていくことを願っている。
でも実際にマンガを描き始めたときには昔とは比べ物にならないほど世の中は便利になっていた。
大塚さんとマンガ本の企画を始めた時から電子メールで通信していた。たまに電話で話したこともあったが、電子メールの方が便利だった(安かったし)。特に都合が良かったのは、私の本業が終わり、うちに帰って夕飯を終わらせてマンガに専念する時間になると、ちょうど日本では労働時間が始まるということだった。
インターネットサービスの転送スピードは上がっていく一方なのでファイルを送る作業もそれに連れて良くなる一方だった。初めのうちはあらすじやシナリオを書いたテキストファイルだけを送っていた。描いたマンガの内容をチェックしてもらう時でもファイルを圧縮していたので、ページあたり1~3メガバイトで済んだ。最終的に印刷所へ送ったハーフトーンされたファイルは白黒であったため、もとの内容チェック用のファイルよりも小さかったので(高解像度な2400DPIであったにも関わらず)ファイルが重すぎたことはなかった(カバーイラストだけはかなりでかく、取り扱いが面倒だった)。
普通の郵便の方が便利だったのは編集作業の時だけだった。大塚さんは細かい編集をオンラインではやらず、プリンターで打ち出したページに赤ペンで編集を入れて国際郵便で送るのが一番簡単だった。
そのようにほぼ初めから最後までインターネットのファイル転送だけで間に合った。それでも何回かは日本に行って大塚さんと顔を合わせた。いつまでもインターネット上のバーチャルだけな存在でいるのも変だし、互いに知り合うためには直接会うのが一番である。
ある訪問中、大塚さんは私をマンガの編集者である清水さんに紹介してくれた。清水さんはあの「少年マガジン」の副編集長だったので、私はどうなるんだろうと少しビビった。でも全く心配することはなかった。彼はとても親切で、私に励ましのアドバイスなどを色々としていただいた。例えば「自分で描くのが面白くなかったり面倒な絵は、読者が読んでもそのように感じる」という知恵は今でも毎日マンガを描きながら意識している。

とても残念なことに、あれからそれほど経たないうちに清水さんは脳溢血で亡くなられてしまった。清水さんは大勢のマンガ家を育ててきた偉大な人である。私はいつも清水さんや父からなどのアドバイスを頭に入れているので、そういう人たちの影響が自分の作品の中で生き続けていくことを願っている。